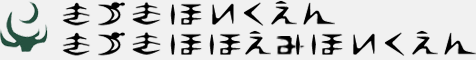ある日、幼児組で食育を行いました。テーマは「冬野菜」でした。食育では、冬野菜にはどんな種類があるのかについて、今日の給食には冬野菜が入っているかなどについてお話しました。
また、野菜のどの部分を食べているかというクイズを行いました。大根を例にどの部分を食べているのかを学んだ後、いろいろな野菜について子どもたちにクイズを出していきました。「ごぼうは、どの部分を食べているのかな?ねっこかな?茎かな?葉っぱかな?花かな?」と私が問いかけると「ほそながいから、くき!」「つちにあるから、ねっこ!」と子どもたちは口々に考えたことを教えてくれました。「正解はねっこでした!」と言うと、正解した子どもたちはやったーと嬉しそうでした。
次に「ブロッコリーは、どの部分を食べているのかな?ねっこかな?茎かな?葉っぱかな?花かな?」と聞くと、子どもたちは悩んでしまいました。「えー、みどりいろだし、はっぱかなぁ?」「くきかもしれないよ」「つちに、はいっていないから、ねっことはちがうのかな?」いろいろな声が聞こえてきます。「実はブロッコリーは花の部分を食べているよ。正解は、花の部分を食べているでした!」と言うと、正解した子は嬉しそうに、そうでない子は少しがっかりした様子でした。「花を食べているの?でもみどりいろだよ?」とある子が言いました。私が「そうだね、不思議だね。ブロッコリーは花を食べていると言いましたが、詳しく言うと花の蕾を食べています。」と言い、ブロッコリーの花が咲いている写真を見せると、はっとした顔をした後、納得した様子でした。他の子どもたちもブロッコリーの花が咲いている写真を見ると、「ほんとうにおはながさいてる!」とみんな驚いていました。
この体験から、子どもたちは今までの体験や思ったことから考えて、ある物事とある物事を関連付け、新しく予想をすることができるのだということを学びました。このことから私たちは子どもたちに全てを教えてしまうのではなく、考える力を育むために待つ時間や全てを教えないことが必要だと思いました。
私たち大人は、子どもたちが子どもたち自身で「これはこうじゃないかな?」「これがこうだったから…こうかもしれない!」と考えた仮説や物事と物事との関わりについて、「正解はこうだよ」とすぐに教えることなく、一度立ち止まって子どもたちの考えていることや頭の中の出来事について想いを巡らせる必要があると感じました。
大人こそが一度歩みを止めて、子どもたちが子どもたち自身で考えた結果に寄り添える接し方を模索していかなくてはならないと感じました。

栄養士 太田