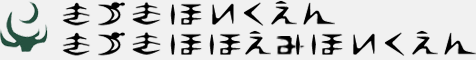1月中旬に移行をし、うきうき組だけでの生活を始めて2ヶ月。卒園式など次々と最後の行事を終え、ついに最終登園日を待つのみとなりました。
2階の幼児組でのびのび、どきどき組と一緒に過ごしていたときは、周りのお友だちを気にかけて困っているとすぐにお手伝いをしてくれていたうきうき組のお友だちですが、移行をしてうきうき組だけでの生活が始まると、なぜか困っているお友だちがいても声をかけなくなってしまいました。
小学校では縦割りより横割りの関係が深くなるので、同い年でもお友だち同士で声をかけ、助け合ってほしいなと思う気持ちと、今まで大人が声をかけなくても自ら気づいてお友だちを助けてくれていたので、みんなが心優しいのは知っていることから、どうして困っている子に声をかけなくなってしまったのかしばらく様子を見てみることにしました。
誰にでも優しくいつも周りを気にかけてくれるAくん。2階で生活していた頃は年下の子の荷物を持ってあげるなど、ほかの子は気づかないことにも気づいて積極的に動いてくれていました。うきうき組での生活の中で「〇〇ができない!」と困っているBくんの様子に気づいている様子ではあるものの、チラチラと見るだけで声をかけることはありませんでした。
Bくんは困ったことがあると私のところにきて「〇〇やってください」と声をかけてくれます。ただ1人担任なのでどうしても手が離せないこともあり、いつも助けてあげられるわけではありません。そこで「お友だちに声かけてみたら?」とBくんに言うと、すぐにAくんが「手伝ってあげようか?」と声をかけてくれました。
このやりとりを見て、Aくんはやっぱり困っていることに気づいていたんだ。何て声をかけたらいいかわからなかったのかな?と思うとともに、自分の今までの言動にハッとしました。
小学校の先生と話をしたときに「できないことがあってもいい。でも、困ったときに助けを求められるようになっていてほしい。」と聞いてから、子どもたちが小学校に入学したあと困らないように、「困ったことがあったら自分から声をかける」習慣をつけられるよう、声掛けをしたり、見守ってきたりしました。その様子を見て、Aくんのような子どもたちも「困っていても声をかけてはいけないんだ」と思ってしまったのかもしれません。
「できないときは何て言ったらいいんだっけ?」「〇〇してください」と困っている子とやりとりをすることが多いですが、これは大人と子どもとのやりとりになってしまいます。
しかし、子ども同士でも助け合えることはたくさんあるはず!と気づいてからは、子どもたちを見守るだけでなく、気づいて行動できるよう援助するようにしています。
困っている子には「わからないときはお友だちに聞いてみる」ことや、「できないときにはお友だちに手伝ってもらう」ことを伝えています。困っている子に気づいてくれた子には「やってあげる」のではなく、「手伝ってあげる」よう声掛けをしています。
そのような援助の仕方を変えてからうきうき組の子どもたちは、わからないことやできないことがあって困っているときに、まずお友だちに声をかけたり、困っている子がいたら「大丈夫?」と声をかけ合える子になりました。
子どもは大人の鏡というように、子どもたちは本当によく大人の行動や言葉を見聞きしています。こういう子になってほしいと思うだけでは子どもたちには伝わらないことを改めて感じ、まずは大人が見本を見せたり、ヒントとなる声掛けをしていかなければならないなと思いました。
うきうき組の子どもたちと過ごした5年間。たくさんのことを学び、一緒に成長することができました。小学校に行っても保育園での学びを活かし、楽しく過ごしてほしいと思います。

梅原