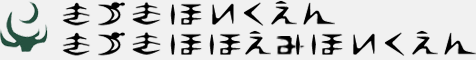木々や花が芽吹き始める様子に、春の訪れを感じる季節となりました。今年度も残りわずか。ぞうぐみの子どもたちは小学生への準備を着実に進めています。2月半ばから地域の小学校3校ほどと小学校交流会がありました。就学に向けて子どもたちの気持ちを高めていくためだったり、小学校でどういったことをしているのかを見て知るということを目的として行います。事前に子どもたちに交流する小学校や日程を伝えると「⚪︎⚪︎小は僕がいくところ!」「⚪︎⚪︎ちゃんに会えるのが楽しみ!」「どんなお勉強してるか知ってるよ!」と興奮気味で、とても楽しみにしている様子が伝わってきました。小学校交流会では小学校によって多少内容は違いますが、1年生のクラスに行き1年生のお兄さんお姉さんに小学校のことを教えてもらったり、一緒にゲームをしたりして交流しました。中には木月保育園の卒園児もいて、久しぶりの再会を喜ぶ姿もありました。どこの小学校も今はタブレットを使って授業を受けているということで、タブレットを用いて校内の紹介をしてくれたり、漢字・計算ドリルを一緒にやらせてくれたりと時代を感じましたが、子どもたちはすぐに順応しタブレットを使いこなしており私たちの方が思わず圧倒されてしまいました。ですが、今回特に驚いたのは子どもたちのお兄さんお姉さんへの関わり方です。ある小学校ではお互いを必ず⚪︎⚪︎さんと苗字で呼び合い、丁寧な言葉を使って会話をしていました。その様子を見ていたぞうぐみの子どもたち。私が交流中の子どもたちのやりとりを近づいて聞いてみると「⚪︎⚪︎さん、これはどうやってやるんですか?」と敬語で1年生に質問をする子。教えてもらって「ありがとうございます」と答える子。「僕は⚪︎⚪︎小学校に来るのでよろしくお願いします」と自ら挨拶をしている子。普段保育園で敬語は使っていませんが、1年生同士のやりとりを見てそこでも順応している子がたくさんいました。また、分からないことがあると自分から聞いたり、恥ずかしくて声が小さくなってしまった子の代わりに名前を言ってあげたりする姿も見られ、まだまだかわいい子どもたちですが、とても頼もしく感じられました。
木月保育園では保育目標として「一人ひとりの発達に目を向け、 相手のことを想い助け合う気持ち(社会性)と、自分で考え行動する気持ち(自主性)を育て、毎日の生活の中で自然に身につけることが出来るように配慮する」を掲げ取り組んでいます。そして例外なくぞうぐみの子どもたちも保育園生活の中で少しずつ少しずつ社会性や自主性、社会生活における望ましい習慣や態度を身に付けてきました。4月からは保育園から小学校と新たなステージへとステップアップするぞうぐみの子どもたち。これからはまた新しい集団生活の場で新しいルールや習慣がたくさんあり、最初は戸惑うこともあると思います。しかし、ここまでたくさんの経験を積んできた子どもたちなら、新しい生活にもすぐに慣れ時に壁にぶつかることもあるとは思いますが、一つ一つ乗り越えて順応していくのではないかなと思います。あと少しで保育園を巣立っていくのは寂しいですが、子どもたちの新生活が輝かしく素敵な日々となることを願いつつ最後の日までみんなで見守っていきたいと思います。ぞう組 松本