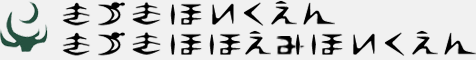まだ肌寒い日はありますが、桃の節句も過ぎ、いよいよ春到来ですね。今回は一時保育のこあら組でのお話をしたいと思います。一時保育では決まった曜日を利用する子、月3回のみ利用する子、月10日のみ利用する子など様々な利用形式があります。月3回のみの利用の子は、曜日利用の子と比べ、すぐに慣れることは難しく、泣いてしまう子が多いですが少しずつ保育士との信頼関係を築き、慣れていきます。私は初めてこあら組の担任になり、通常クラスとは違った子どもの姿をいろんな形で知ることができました。月少ない利用回数の子も、園の生活習慣を覚えている姿に驚きました。園庭から部屋に入った時のことです。毎日過ごしていると、いつもやっていることが当たり前だと思ってしまいがちですが、園庭から帰ってくると部屋に入ったら水道に向かい、手を洗おうとする子どもたち。1歳児のAちゃんと2歳児のBちゃんが水道の前に立っていました。Bちゃんが自分で手を洗っている姿を見て、Aちゃんは蛇口を捻り、手を洗おうとしていました。
そんな園生活の習慣を覚えている子どもたちの姿を見て、どうして覚えていくのだろうと考えてみました。初めは保育士が「お外から帰ってきたら手を洗うよ」と声を掛けながら、一緒に手を洗ってやり方を伝えていきます。そこから自分でできるようになると「手を洗ってね」と声を掛け、自分で水道で手を洗うことを促します。そこからなぜ子どもたちは習慣を身につけることができるのでしょうか。それは大人や周りのお友だちの「模倣」をすることで身につけることができているのではないかと考えました。調べてみると、保育で使われる模倣とは、”成長や学習において非常に重要な役割を果たします。子どもは周囲の大人や友だちの行動、言葉、表情などをまねる(模倣する)ことで、社会的なスキルや言語、文化的なルールを学んでいきます。”と出てきます。このことを踏まえ、子どもたちはまねっこをしながら生きる力を獲得していくのだと思いました。大人や周りのお友だちがやっている姿をみて、やってみたい、まねっこしてみたいという段階を踏んで自分の力を身につけていきます。模倣を活かすためのポイントは、大人が良いお手本を見せること。子どもは親や周囲の行動をそのまままねるため、大人がポジティブな行動を心がけることが大切です。また、失敗を責めずに見守ること。最初はうまくできなくても、何度も模倣することで成長するので、温かく見守ることも重要です。そして、遊びや体験を通じて学ぶ機会を増やすことも大切です。自由に模倣できる環境を作ることで、子どもの成長を促せるのです。子どもの模倣は、ただの「まね」ではなく、成長のための大切な学習手段です。大人が良いお手本を示し、模倣を通して子どもが豊かな経験を積めるようにしていきたいと思います。こあら組 服部